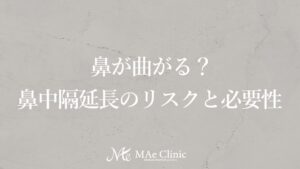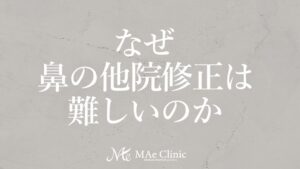鼻整形を検討されている患者さんから、カウンセリングの際によく聞かれる質問のひとつが、
「肋軟骨なら曲がらないんですよね?」
というものです。
たしかに、肋軟骨は耳介軟骨や鼻中隔軟骨と比較しても強度や厚みがあり、形状の安定性も高いため、構造的に非常に信頼性の高い移植材料です。特に、鼻中隔延長や鼻背形成のように、しっかりと支える構造物が必要な場面では欠かせない素材となっています。
しかし、残念ながら「肋軟骨=絶対に曲がらない」というわけではありません。実際には、肋軟骨であっても時間の経過とともに反り返ったり、ねじれたりする「ワーピング(Warping)」という現象が起こることがあります。
本記事では、形成外科専門医・美容外科専門医の立場から、
- 肋軟骨でワーピングが起こるメカニズム
- それを防ぐための術式上の工夫
- 修正が必要になるケースと実際の症例
- 再手術の注意点と術後管理
について、解説していきます。
ワーピングとは何か?
ワーピング(Warping)とは、軟骨や人工物などの移植材料が、時間とともに本来の形から反り返ったり湾曲したりする現象を指します。
鼻整形では、次のような形で現れます。
- 鼻筋がS字状に歪む
- 鼻柱が左右に傾く
- 鼻先が片方に流れてしまう
- 鼻の中心軸が曲がり、顔全体の印象が崩れる
この現象は、特に細長く加工された軟骨で起こりやすく、鼻中隔延長や鼻背形成における長軸方向の使用が多い部位では注意が必要です。
ワーピングは術後1〜3ヶ月以内に起こることが多いですが、半年〜1年を経てから変形が現れることもあります。そのため、術後早期の経過だけで判断せず、長期的な構造設計が求められる分野です。
なぜ肋軟骨でもワーピングが起こるのか?
1. 弾性記憶(形状記憶)
肋軟骨は生体内では弓状にカーブしており、移植用に真っ直ぐ削っても、時間が経つと元の形に戻ろうとする“反発力”が働きます。これが「弾性記憶」と呼ばれるもので、肋軟骨特有の強さと同時にワーピングのリスクにもなります。
2. 加工の左右差・非対称性
軟骨を斜めに切り出したり、片側だけを多く削ってしまうと、内部の張力バランスが崩れて片側に引っ張られるような力が生じます。これが原因で軟骨が反ったりねじれたりします。
3. 術後の癒着や圧迫による変形
術後の組織癒着や圧迫が一方向にかかることで、軟骨が変形してしまうこともあります。これは軟骨そのものの問題ではなく、周囲組織との力学的なバランスの問題です。
ワーピングが起きたらどうなる?
ワーピングが軽度であれば、外見上あまり気にならないこともありますが、以下のようなケースでは修正手術が必要になります:
- 鼻筋に明らかなS字カーブがある
- 鼻柱が左右どちらかに傾いている
- 鼻先が片側に流れている
- 顔の中心軸がずれて見える
また、「他人にはわからないけれど、自分ではずっと違和感がある」と感じる方も多く、そうした微妙な歪みも修正の対象となることがあります。
修正において重要なのは、どの方向にどのような力がかかっていたのかを見極めること。構造の中で力がどこに逃げ、どこに集中したのかという力学的な視点が求められます。これは、形成外科的な訓練と経験を積んだ医師でないと判断が難しい部分です。
実際の症例:ワーピングと構造崩壊による斜鼻を修正したケース




こちらは、過去に何度か鼻整形を受けておられた患者さまの修正症例です。最終的には、プロテーゼと肋軟骨を併用した鼻中隔延長が行われていましたが、両顎骨切術の影響もあり、顔の骨格自体が傾いた状態となっていました。
その結果、鼻の土台ごと斜めに引っ張られるような形で、
- 鼻筋はS字にねじれ、鼻柱は左右非対称に
- 鼻中隔が潰れ、鼻腔が狭窄し呼吸が困難に
- 鼻先の向きや鼻孔の縁も左右差が目立つ状態
といった機能面と審美面の両方に大きな問題を抱えておられました。
構造的再建術の内容
このような複雑な状態に対して、当院では以下のような修正術を行いました。
- 潰れた肋軟骨のストラットを抜去し、軟骨を新たに再構築
- 鼻中隔を骨膜ごと骨に固定し、軸がぶれないよう再設計
- 曲がりと拘縮の原因となっていたプロテーゼを完全に抜去
- 鼻先は軟骨と筋膜を用いて、左右対称かつ自然なラインを形成
1年間の経過観察を経て、呼吸機能の回復と見た目の改善の両立が確認され、患者さまも無事に“鼻整形から卒業”となりました。
この症例のように、肋軟骨やプロテーゼといった移植材料そのものの変形に加え、骨格や組織間のバランスが崩れたことで起こる“構造的なワーピング”は、単なる見た目の左右差だけでは済まされないケースがあります。
そのため、再建手術では「どこを修正するか」ではなく、「どの力がどの方向に働いた結果、構造がどのように崩れていたか」を読み解く力が求められます。
ワーピングを防ぐための当院の工夫
ワーピングを完全にゼロにすることは難しいですが、当院では以下のような多角的アプローチにより、リスクを限りなく低く抑えるよう努めています。
1. 湾曲の少ない部位から軟骨を採取
肋軟骨は部位によって弯曲の強さが異なります。比較的直線に近く、反りが出にくい第7〜9肋骨から軟骨を選び、曲がり癖の強い部位は避けるようにしています。
2. 軟骨の彫刻は「中立軸」を意識して行う
軟骨を削る際には、左右のバランスを保ち、中立軸(ニュートラルゾーン)を中心に対称的に加工することで、内部応力の偏りを防ぎます。わずかな左右差でも将来的な反り返りにつながるため、ミリ単位での調整が重要です。
3. 層状に積層する「ラミネート技術(Laminated Graft)」
反りの向きを逆にした軟骨を重ねて固定することで、お互いの反発力を打ち消し合い、安定性の高い構造に仕上げます。これは鼻中隔延長のライン形成において特に有効です。
4. 骨膜固定と多点支持による安定化
鼻中隔延長では、鼻中隔軟骨や鼻骨にしっかり固定する設計を行います。また、1〜2点止めではなく多点支持で面として支えることで、術後のズレや回旋を防止します。
5. 表層処理によるなじみの調整
皮膚が薄い鼻先などには、必要に応じて骨膜を表層に重ねて軟骨の輪郭をぼかす処理を行います。これにより、触感や見た目の柔らかさも確保しつつ、変形リスクも軽減します。
6. 圧迫・癒着を防ぐ術後管理の徹底
手術後の軟骨が外力や癒着で変形しないよう、固定テープやギプスの使用法、安静期間、経過観察のタイミングまで、段階的に管理しています。
これらの工夫はすべて、「一時的に綺麗」ではなく「1年後、5年後まで安定した形」を見据えて行っています。
よくある質問(Q&A)
Q. 肋軟骨でも曲がると聞いて不安ですが、やめたほうがいいですか?
A. 肋軟骨は強度・安定性の点で非常に優れた材料ですが、術者の扱い方によって結果が左右されます。正しく設計・固定すれば、非常に信頼できる材料です。
Q. ワーピングは誰にでも起きるのですか?
A. 体質・軟骨の癖・固定方法・周囲の癒着などさまざまな要素が関わります。完全に防ぐのは難しくても、設計と術後管理で大幅にリスクを下げられます。
Q. 再手術は一回で綺麗になりますか?
A. 元の変形の程度や内部構造の状態によって異なりますが、一度で安定した形に戻すために綿密な設計が必要です。
術後の管理と再手術の注意点
再建手術や修正術では、手術そのものだけでなく、術後の管理が極めて重要です。
- 術後の腫れや圧迫で軟骨が押されないようにする
- 一定期間は強い表情運動を避ける
- 1〜2週間目の経過観察、1ヶ月・3ヶ月・半年と段階的な診察
- 長期的な軟骨の変形や癒着の兆候を確認
といったフォローが必要です。特に、過去に何度か手術をしている方は、内部の瘢痕や癒着が強くなっていることも多いため、細心の注意が必要です。
まとめ
どんなに優れた素材であっても、肋軟骨であっても、術後にワーピング(変形)が起こる可能性はゼロではありません。 その原因には、軟骨自体の形状記憶、加工の精度不足、固定の不安定さ、術後の癒着や圧迫など、複数の要素が複雑に関係しています。
これを未然に防ぐには、素材の選定段階から術後の管理に至るまで、すべての工程を“構造の安定性”という視点で設計・管理する必要があります。
一度ワーピングが起きてしまった場合でも、力のかかり方や軟骨の状態を丁寧に分析し、適切な再建設計を行えば、修正は十分可能です。 そのためには、構造医学と力学的理解、そして修正経験の豊富な医師による手術が欠かせません。
当院では、骨格や軟骨の状態を診察で見極めたうえで、患者さま一人ひとりに最適な手術プランを構築しています。 僕自身、これまで初回手術だけでなく、他院修正や複雑な再建術も数多く手がけてきました。
「鼻筋が歪んできた」「軟骨が曲がっている気がする」「他院修正を検討している」
これから鼻整形を考えている方も、すでに手術を受けた方も、 構造から安定性を見直したいという方は、ぜひ一度ご相談ください。
“構造”にこだわった鼻整形で、長期的に美しく安定する結果を目指しましょう。